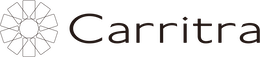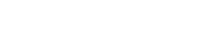ダイバーシティ推進担当者向け|両立支援を「女性活躍」だけでなく「働きがい改革」につなげる
2025.10.31
- お知らせ
ダイバーシティ推進担当者向け|両立支援を「女性活躍」だけでなく「働きがい改革」につなげる
前回は、育児介護休業法改正の背景と女性管理職の少なさの要因を紐解いていきました。
今回は、企業が両立支援を進めることで得られるメリットと、ダイバーシティ推進担当者が意識すべき視点について一緒に考えていきましょう。

diversity of hands touching each other in circle design, people multiethnic race and community theme Vector illustration
<a href=”https://www.vecteezy.com/free-vector/diversity”>Diversity Vectors by Vecteezy</a>
企業が両立支援を進める事で得られるメリット
両立支援は、「女性のため」の施策ではありません。従業員一人ひとりがライフステージに応じて安心して働ける環境を整えることは、「働きがい改革」の重要な一歩です。
- 優秀な人材の確保と定着
育児や介護を理由に離職する人材を減らすことは、企業にとって大きなメリットです。特に、経験を積んだ中堅層の離職は、職場の知見やノウハウの損失につながります。両立支援を整えることで、従業員が安心して働き続けられる環境が生まれ、働きがいのある職場づくりが進みます。
- 多様な視点の活用によるイノベーション
育児・介護を経験する従業員は、生活者としての視点を持っています。こうした多様な視点が組織に取り込まれることで、商品開発やサービス改善に新たな発想が生まれやすくなります。働きがい改革とは、従業員の経験や価値観を尊重し、活かすことでもあります。
- 従業員のエンゲージメント向上
両立支援に積極的な企業は、従業員からの信頼を得やすくなります。「この会社で長く働きたい」「自分の人生も大切にできる」と感じられる職場は、働きがいの高い職場です。人的資本経営が注目される今、従業員の働きがいを重視する企業姿勢は、持続可能な組織づくりにもつながります。
ダイバーシティ推進担当者が意識すべき視点
両立支援を単なる制度導入で終わらせず、企業の文化として根付かせるためには、どような視点が必要でしょうか?
①制度の「使いやすさ」まで設計する
制度があっても、使いづらければ意味がありません。上司の理解、職場の雰囲気、業務の引き継ぎ体制など、制度の運用面まで見直すことが必要です。
②男性の育児参加も支援する
育児介護休業法改正のポイントにもなっていますが、両立支援は女性だけのものではありません。男性の育児参加を促すことで、家事育児の負担を分散し、女性のキャリア形成を後押しすることができます。これは、ジェンダーダイバーシティの観点からも重要です。
③「両立=特別扱い」ではない文化づくり
両立支援を受ける従業員が「申し訳ない」と感じる風土では、制度は定着しません。誰もがライフイベントを迎える可能性があることを前提に、支え合う文化を育てることが重要です。
④働きがいの視点で施策を見直す
制度の目的を「離職防止」や「法令遵守」だけでなく、「働きがいの向上」として捉えることで、施策の設計や社内への伝え方・伝わり方が変わります。従業員が「ここで働き続けたい」と思える環境づくりが、ダイバーシティ推進の本質です。
ここまで、両立支援を働きがい改革という切り口で考えてきました。
組織の制度設計や、社員への伝え方を考える際にも、こういった視点を取り入れてみてはいかがでしょうか?
【お問い合わせ】
キャリアトランプ R認定校 ラポール校
運営:株式会社ラポール
TEL: 048-682-0066(月~金 9時‐18時)
Email: contact@human-v.co.jp
written by ラポール校
NEW POST
CATEGORY
ARCHIVE
お問合せ
お問合せ・ご相談など、お気軽にご連絡ください。
052-439-6337